映画「オオカミの家」。
クリストバル・レオンとホアキン・コシーニャの二人組による初の長編アニメ。
チリに実在したドイツ人のコミュニティ「コロニア・ディグニダ」を、インスパイアしたホラー映画となっている。
アニメーションとストップモーションを駆使し、冒頭から観客を不安にさせる演出の連続はホラーというよりもはやアート。「ミッドサマー」の監督アリ・アスターが絶賛したように、異質な恐怖を体験できる。
観客を驚かせるような演出はなく、不気味でねっとりまとわりつくようなイヤーな恐怖を感じられる作品になっている。
カルトコミュニティから逃げてきた少女マリアが、2匹のブタと出会い、奇妙な悪夢を見る話。
どこまでが、現実でどこからが悪夢なのか境目のつかず、次々に変わりゆく情景はストーリーをわかりにくもしている。
「オオカミの家」の元となったおぞましいコミュニティ「コロニア・ディグニダ」の解説に加えて、アートのような世界で何が行われていたのかを説明していく。
オオカミの家
(2023)

3.3点
ホラー
クリストバル・レオン、ホアキン・コシーニャ
アマリア・カッサイ
- ストップモーションで制作された狂気のホラー
- コミュニティ逃げた先の隠れ家で2匹の子豚と暮らす女の子の話
- 実在するカルト教団のコミュニティからインスパイアされた怖いグリム童話
- アートとしては最高だが、ストーリーはわかりにくい
定額で映画をレンタルするならゲオ

「ゲオ宅配レンタル」は無料トライアルに登録すると特典が2つ!
- VODよりも安く借りられる
- 家にいながらレンタル、返却はポストに入れるだけ
- 月額プランなら返却期限なし!
- 月額プランなら送料・延滞料金¥0
\ 35万本のDVDが見放題! /
映画「オオカミの家」ネタバレ考察・解説
「オオカミの家」のあらすじ
(C)Diluvio & Globo Rojo Films, 2018
「オオカミの家」はアニメーションとストップモーションを利用して家の内部やマリアたちの表情を描き出す。ストップモーションで描かれた多様で異様な表情は、とても不気味である。
本来、ホラー映画は主人公視点で恐怖を観客に伝えることが多いが、「狼の家」ではストップモーションで作られたマリアの表情からして怖い。感情を表現しながらも本質は無感情なマリア自身に恐怖を感じるつくりになっている。
また、次々に変わりゆくストップモーションの映像は、アートの要素が盛り込まれていて、観客の注意を惹きつけるものである。代わりにアートが行き過ぎていてそのストーリーは観客を混乱させるつくりだ。
物語の冒頭、マリアは3匹の豚を逃してしまい、100日間会話禁止の罰を受ける。その罰に嫌気がさしたマリアはコロニーから逃げ出し先で、とある家に隠れる。
そこで出会った2匹の子豚の世話を始めるという話。
ストップモーションといういびつな演出が物語を奇妙にしていくが、さらに不気味なのが飼っていた2匹の豚が、ある日人間の姿に変わるところだ。
外には狼がいるため3人は家から出られない。話さない、いや話せない元豚にペドロとアナという名前をつけ、そのまま3人の時間は過ぎていく。彼女たちは幸せに暮らし始める。
次々に場面展開していくが、アニメーションとして描かれたりリアルな人形として描かれたりでマリアたちの表情は読み取りにくい。ただ、途中までは3人で仲睦まじく暮らしているというのがなんとなく理解できる。
外には狼がいるために家の中の食料は減っていくことで、だんだんと3人は飢えていく。とうとう、外に出て食べ物を取りに行こうとしたマリアだったが、アナとペドロは反対し、マリアを縛り付けてしまう。
そして最終的には飢えにより、アナとペドロはマリアを食べようとするのだ。
このストーリーを紐解く重要な要素は、「コロニア・ディグニダ」という閉鎖的なコミュニティに密接に関係している。
コロニア・ディグニダとは
(C)Diluvio & Globo Rojo Films, 2018
インスパイア元となったコロニア・ディグニダは、チリに実在したコミュニティで、元ナチス党員であるドイツ人、パウル・シェーファーが設立したカルト教団である。
1960年初頭から約40年続いた閉鎖的なコミュニティは、外部の人たちからは完全に秘匿され、地元の人にとってはお化け屋敷のような場所であり、何が行われているのか分からなかった。
しかし、内部では絶対的な権力をもつシェーファーによる拷問や性的虐待が行われていたという。
家族は分離され、話すことも禁じられた。小学生になる年には強制労働に従事させられ、性的虐待が続けられていた。コロニーの中は常に監視され、家族が離ればなれにされることで助けることもできなかった。
労働・秩序・精錬さを求め、農業に従事しながら暮らしていくコミュニティは、外界からしたら美しく人間的に見える。
しかし、実態は独裁者が独善的行為を行うことで、住民たちの人権などない場所だった。
「オオカミの家」は、そんなおぞましきコミュニティから逃げてきた少女が、新たな「家」でコミュニティを作っていく話である。
テーマとラストの意味
(C)Diluvio & Globo Rojo Films, 2018
「オオカミの家」はコロニア・ディグニダの閉鎖的なコミュニティによるカルト的支配の要素を取り入れている。
マリアたちが恐れていたオオカミという存在であるが、マリアにとって「恐怖の対象」として描かれたものであり、実際にオオカミが外をうろついているわけではない。
オオカミはマリアにとっての恐怖の象徴であり、「コロニア・ディグニダ」のコミュニティそのものを指している。
その恐怖をオオカミに置き換えて、新しい家(コミュニティ)でアナとペドロに刷り込んだのはマリア自身だ。「家」の中ではマリアが世界のすべてであり、2人はマリアの教えが正しいと信じている。
つまり「オオカミ」であるコロニーを離れたマリアは、新たな「家」で同じコロニーを作り出すのだ。そこではマリア自身が絶対的な支配者となる。マリアは「家から出たらオオカミに食べられる」と話し、言うことの聞かない犬の絵本を読み聞かせ、従わないことを悪と植えつける。
マリアは、アナとペドロに自分の価値観を植え付けた。他の価値観が入らない場所では、それは2人とっての聖書となりうる。
物語の中盤、アナとペドロはマリアのように青い目と金髪の姿に変わっていく。従順でマリアにとって都合の良い人間に変わったことを示唆している。
マリアは2人を愛し、献身的に世話をしていたはずだった。しかし、絶対的君主しかいない場所では、新たな価値観は入らないまま固まってしまう。
歳をとるにつれて、思考が固まってしまう人が多くなるのは、今まで生きてきた価値観を正しいと思い込み、新しい思想を受け入れられなくなるためである。
絶対的な正義で洗脳すると、そこには歪みが生まれる。矛盾は許されず、そのルールから外れるものは悪い行為だとみなされる。
だからアナとペドロは食料が少なくなり、マリアが食料をとりにいくといっても許さずに縛り付けてしまう。外は危険がいっぱいで、家を出たらオオカミに食べられてしまうという教えを忠実に守っているためだ。
コロニア・ディグニダを想起させる「オオカミ」からの脱却を目指した「家」であるが、すでにオオカミに洗脳されていたマリアが入り込むことで、その「家」もカオスな場所に置き換わる。
人間を洗脳し、支配するカルト教団で育てられたマリアは、逃れられない悪夢に取り憑かれたままなのである。
カルト教団の中にいるとそこがすべてのように感じてしまう。その小さな世界は外界に閉ざされ、価値観がアップデートされることなく思考がこりかたまっていく。
コミュニティから従わずに逃げてきたマリアだったが、「家」が恐怖の場所にとって変わることで、最終的には「オオカミ(コロニア・ディグニダ)」に助けを求めるようになる。
住む「家」が悪いのではなく、自分自身の振る舞いが悪いのだと悟ったマリアは、この事実を受け入れてコロニア・ディグニダに戻るのだ。
マリアは閉鎖空間を作り出し、アナとペドロを洗脳してしまった。彼女たちが生きていくには導いてくれる誰かが必要だった。
3人が木に変わっていく姿は、人間や動物のような意志を持たず、ただそこに存在し教団の一部として無抵抗に働き続けるという未来を表しているとも読み取れる。
ストップモーションを多用した本作は、マリア自身も不気味に描く。これはマリア自身がすでに一部の先入観や価値観にとらわれて洗脳された後であり、私たち観客に閉鎖空間で人はいかに狂うのかという恐怖を与える。







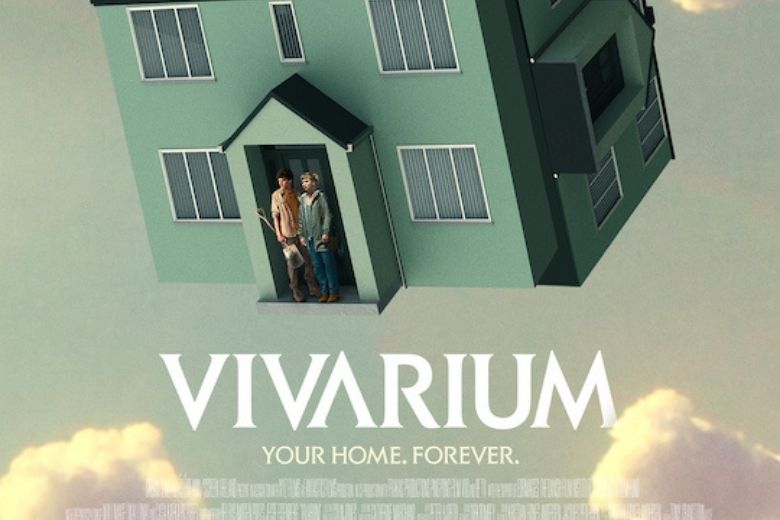










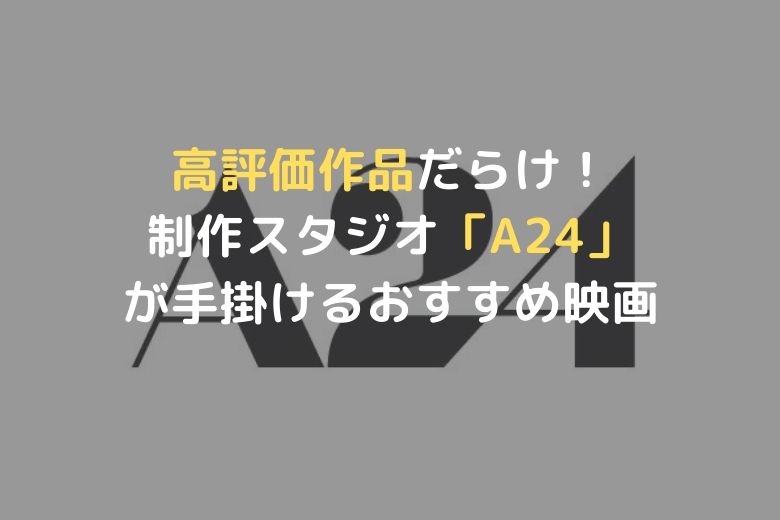


コメント