あまりにも長く苦痛な時間だった。
鑑賞したのは「フレンチ・ディスパッチ」。
「グランド・ブダペスト・ホテル」「犬ヶ島」のウェス・アンダーソン監督が、フランスの架空の街にある米国新聞社の支局で働く個性豊かな編集者たちの活躍を描いた長編第10作。
ウェス・アンダーソンらしいジオラマの世界観やカートゥーン調の映像、モノクロとカラーの色彩をうまく使った映像美は素晴らしい世界観だった。
一方で、ストーリーは尋常じゃないほどにつまらない。意味のない映像を延々と見せられているだけでなくセリフによる情報量も多い。しかし、そのセリフまわしも伏線もなければストーリーに繋がってもいない。
脳のキャパを超えたあげくなにも得るものはない。
物語性を重視する人には絶対に勧められない。ひたすらにストレスのかかる映画だった。
「フレンチ・ディスパッチ」

損しないサブスク動画配信の選び方
映画を観る機会が多い方のために、損しないサブスクの選び方を教えます。
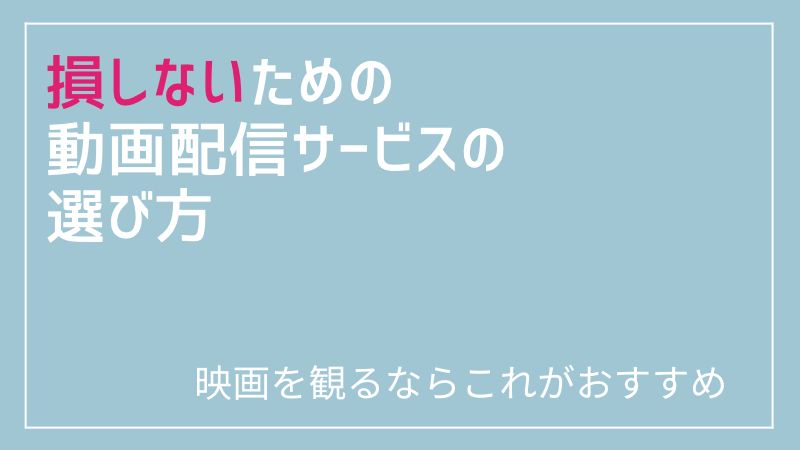

「フレンチ・ディスパッチ」映画情報
| タイトル | フレンチ・ディスパッチ |
| 公開年 | 2022.1.28 |
| 上映時間 | 103分 |
| ジャンル | 恋愛 |
| 監督 | ウェス・アンダーソン |
映画「フレンチ・ディスパッチ」キャスト
| 登場人物 | キャスト |
|---|---|
| アーサー・ハウイッツァー・Jr | ビル・マーレイ |
| J・K・L・ベレンセン | ティルダ・スウィントン |
| ルシンダ・クレメンツ | フランシス・マクドーマンド |
| ローバック・ライト | ジェフリー・ライト |
| ルブサン・サゼラック | オーウェン・ウィルソン |
| モーゼス・ローゼンターラー | ベニチオ・デル・トロ |
| ジュリアン・カダージオ | エイドリアン・ブロディ |
| シモーヌ | レア・セドゥ |
| ゼフィレッリ・B | ティモシー・シャラメ |
| ジュリエット | リナ・クードリ |
| 警察署長 | マチュー・アマルリック |
| ネスカフィエ | スティーヴン・パーク |
| 運転手ジョー | エドワード・ノートン |
| ショーガール | シアーシャ・ローナン |
映画「フレンチ・ディスパッチ」あらすじ
国際問題からアート、ファッション、グルメに至るまで深く切り込んだ記事で人気を集めるフレンチ・ディスパッチ誌。編集長アーサー・ハウイッツァー・Jr.のもとには、向こう見ずな自転車レポーターのサゼラック、批評家で編年史家のベレンセン、孤高のエッセイストのクレメンツら、ひと癖もふた癖もある才能豊かなジャーナリストたちがそろう。ところがある日、編集長が仕事中に急死し、遺言によって廃刊が決定してしまう。
eiga.com
映画「フレンチ・ディスパッチ」ネタバレ感想・解説
(C)2021 20th Century Studios. All rights reserved.
「フレンチ・ディスパッチ」の舞台はフランスのミッドセンチュリー時代の話。
「New Yorker」という雑誌がモデルになっていて、「フレンチ・ディスパッチ」に登場する編集長のアーサー・ハウイッツァーは「New Yorker」の創始者ハロルド・ロスをモチーフにしている。
1925年に創刊されたこの雑誌は現代でも続く老舗の週刊誌である。
「フレンチ・ディスパッチ」はウェス・アンダーソン監督の「New Yorker」に対する敬意がふんだんに現れた作品であり、そこに実在した著名な編集者たちも登場する。
数々のオマージュ?が作中に現れるため、この映画の物語性を楽しむには「New Yorker」に対する十分な知識が必要である。
「New Yorker」という雑誌を知らない私には、もはやこの映画を楽しめる要素が根本的が足りていないのだ。
物語は全部で4つのストーリーで構成されている。
「New Yoker」ならぬ「フレンチ・ディスパッチ」は、フランスのミッドセンチュリー時代最後の出版を刊行する。その選ばれた4つの記事を劇画調に語っていく流れだ。
なのでそれぞれの物語はこれといってリンクしていない。
1つ目はトラベルレポーターのサイクリングツアー。架空の街を自転車で巡りながら今と昔の対比をさせていく。世界観を観客に伝えるのに重要なパートでもある。
2つ目は殺人を犯して重罪の刑に処されているベニチオ・デル・トロ扮するモーゼス。彼は類稀なる才能をもつアーティストの側面を持っており、そのことを知った起業家のカダージオ(エイドリアン・ブロリー)が作品を描いて欲しいと依頼する。
この記事の編集者はJ・K・L・ベレンセン(ティルダ・ウィンストン)。彼女は映画の中で観客にモーゼスのアートについてプレゼンしながらストーリーテリングをしていく構成だ。
3つ目はゼフィレッリ(ティモシー・シャラメ)という学生運動のリーダーを追いかけるレポーターのクレメンツ(フランシス・マンドーマンド)が、その運動に巻き込まれていく話。
そして最後に警察内部にいるシェフと誘拐の話。
この4部作のうちの序盤、ベニチオ・デル・トロの話でもう睡魔が襲ってきた。
さらに3つ目の話に移ったころには見ることが苦痛でしかなくなり、4つ目は涅槃の境地に至る心地だった。
(C)2021 20th Century Studios. All rights reserved.
そういうわけでストーリーがとにかくつらい。
これでもかというほどに苦痛だった。私にとって映画をみるモチベーションの多くを占めるのは物語性だ。
役者や演出、撮影技法なんかは、物語の彩りにはとても重要な要素である。引き立て役というほど小さな役割ではないことは承知しているが、少なくとも物語の軸は絶対的に必要だ。
だから映画がどれだけアーティスティックであり、どれだけ演出が優れていようとも、物語が何もないのであれば苦行でしかないのだ。
ストーリーは確かにあるが、意味がない。それぞれの記事も関連性がない。あくまで「フレンチ・ディスパッチ」という雑誌の優れた編集者たちが作った1つの記事という扱いでしかない。
伝えたいメッセージなんてものは皆無だ。その代わりにこれでもかというほど芸術を見せつけてくる。
役者たちも何をさせられているのか理解できないのではなかろうか。
演出は素晴らしい。芸術がなんたるかを知らない素人でもわかる。才能に満ちあふれていて、どういう想像力を働かせたらこれだけのことができるのかわからない。
1つ1つのシーンがシンメトリーになっていて、すべての構図は計算されている。
モノクロの中にときどき差し色として挿入される色の使い方のセンスや、静止画のように見せておいて実は役者たちが止まっているように見せているだけなどのシュールなユーモアのある演出も楽しい。
急にくるカートゥーンを使ったカーチェイスなんかも見ていてほっこりした。
ジオラマのような世界観はウェス・アンダーソン監督の頭の中にしか存在しない唯一無二のユーモラスな映像であるには間違いない。
だからこそ、”ひとかけら”ほどのおもしろさもないストーリーには非常にまいった。
(C)2021 20th Century Studios. All rights reserved.
美術館に迷いこんだかのようで、ひたすらよくわからないけどセンスの塊のような絵を見せられている気分だった。
1つ1つの絵にはとびきりのセンスを感じるし、畏敬の念すら生まれるほど尊さを感じる。
しかし、2時間弱もの間、センスの塊を見ているだけでは凡人には苦しい。なにかしらストーリーテリングがなければ集中力は続かない。
そしてこの映画のラストがどうだとか、伏線がどうだとか語る気にもならない。
ウェス・アンダーソンの作品展であればぜひいきたいが、映画という媒体の中で物語を楽しむことを目的だとするともう見たくない。
芸術的な映画も嫌いではないが、「フレンチ・ディスパッチ」の世界観では言葉による情報量も多い。その意味を考えても考えても意味がないものだから、脳みそが完全にクタクタになってしまった。
この映画を何回か見ればいずれ愛着が湧き、病みつきになり、さらにはこのセンスの一部が自分の血肉になっていくはずだ。
それだけ素晴らしい才能がある映画だというのは、何もわからず酷評をしているだけの私でもわかる。
しかし、私にはこの映画の2回目を見る根気は残っていない。
大きな敗北感を味わうこととなる映画だった。


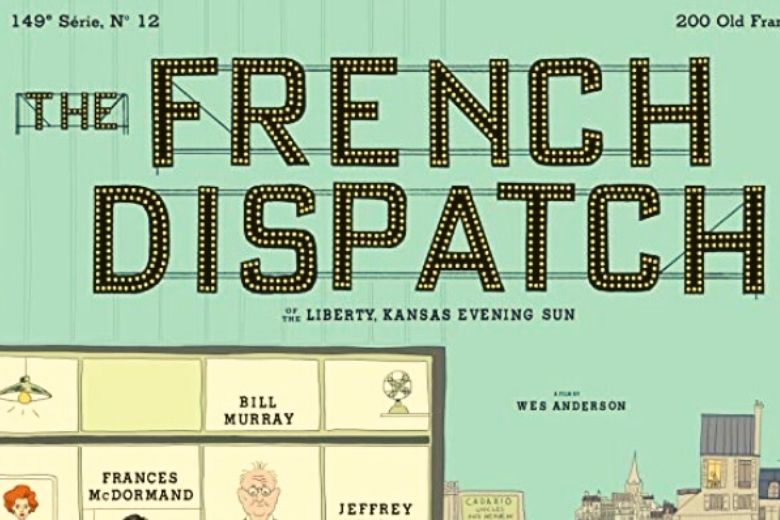








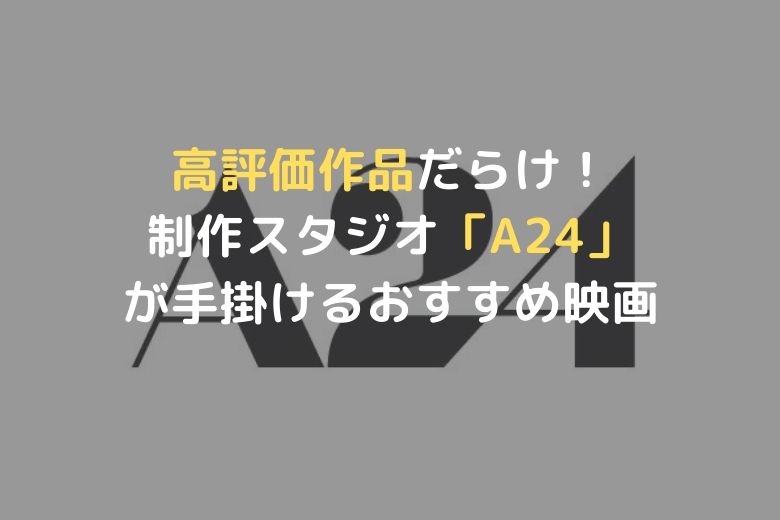


コメント